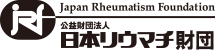EULAR 2025
(五十音順)
聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 高桑 由希子
1.はじめに
2025年度国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成費にご採択いただき、誠にありがとうございました。2025年6月12日にスペイン・バルセロナで開催されたEULAR 2025(Annual European Congress of Rheumatology)にて、2演題のポスター発表(うち1演題はポスターツアーでの口頭発表)を行う貴重な機会を得ることができました。2013年マドリッドEULAR以来、約12年ぶりの国際学会参加となり、大変有意義な経験となりましたことを、心より感謝申し上げます。
2.発表演題の概要
Ⅰ:POS0149
演題:Treatment Strategies for Achieving Steroid-Free Management in Refractory Relapsing Polychondritis Using Biologics
発表形式:ポスターツアー(ガイド付き口頭発表、英語、4分発表+2分質疑応答)
概要:難治性再発性多発軟骨炎(refractory RP)患者56例におけるTNF阻害薬およびIL-6阻害薬の導入時期と治療持続性、ならびにグルココルチコイド(GC)フリー寛解の達成率を検討しました。IL-6阻害薬は長期の治療維持とGC離脱に有利であり、TNF阻害薬は導入初期に適する可能性が示唆されました。導入期TNFi → 維持期IL6iが今後の治療戦略になる可能性が否定できません。
学術的意義:日本国内でも稀なRPに対する比較的規模の大きい臨床データであり、特にGCフリーを目指す新たな戦略の提示は、国際的にも高い関心を集めたと感じました。
Ⅱ:POS0895
タイトル:Impact of Methotrexate Administration Routes on Cumulative Medical Costs and Polypharmacy in Rheumatoid Arthritis: Insights into Shared Decision Making in the Initial Treatment Phase
発表形式:通常ポスター掲示(現地掲示・現地説明対応)
概要:関節リウマチ初期治療におけるメトトレキサート(MTX)経口投与群(PO)と皮下注投与群(SC)を比較し、累積医療費、ポリファーマシー、グルココルチコイド使用状況、およびShared Decision Making(SDM)の実態を評価しました。
SC投与群では寛解到達が早く、BIO/JAKi導入率が低く、結果的に累積医療費も有意に低下しました。また、PO群ではSDMにおいて医師と患者の認識ギャップが大きく、治療方針決定におけるコミュニケーションの重要性が改めて浮き彫りとなりました。
学術的意義:初期治療における投与経路の選択が、長期的な医療資源の効率化と患者アウトカムに影響することを示唆し、医療経済および患者中心の医療に貢献する内容であったと感じました。
3.学会参加を通じた経験と今後の展望
今回、POS0149演題でポスターツアーという特別な口頭発表の機会をいただいたことは、自身の研究内容を海外の専門家に直接紹介し、質疑応答を通して多くのフィードバックを得る大変貴重な経験でした。特に、RPという稀少疾患の治療戦略について、欧州の研究者や臨床家から関心と意見をいただき、今後の研究や戦略構築に大きな刺激となりました。
また、久しぶりの現地参加となるバルセロナでは、サグラダ・ファミリアの見学も叶い、医療と文化の双方において視野が広がる体験ができました。
EULARのような国際学会では、私達の診療や研究を相対的に見つめ直す貴重な機会となりました。こうした学びを、今後の後輩指導にも活かしていきたいと考えております。
4.最後に
本助成金を通じて得られた国際学会での発表経験は、今後の研究・診療・教育活動の糧となる貴重な財産です。改めて、日本リウマチ財団のご支援に心より感謝申し上げます。今後も国際学会で発表できるような研究成果を積み重ね、グローバルな視点でリウマチ診療の質向上に貢献出来るよう努めていきたいと思います。
京都大学医学部附属病院リウマチセンター 中坊周一郎
この度私は令和7年度「国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成」を賜り、スペインはバルセロナで令和7年6月11日から14日の4日間にわたって開催されましたEULAR 2025に参加させていただきましたのでここにご報告させていただきます。
私は大学院生の頃から主に関節リウマチの自己抗体にまつわる蛋白の翻訳後修飾、特にカルバミル化について研究を行ってまいりました。今回の発表内容は昨年8月まで留学していたアメリカ国立研究所(NIH)で行った仕事がメインで、抗カルバミル化蛋白抗体が関節リウマチの骨破壊に関係する機序についてoral presentation形式で発表させていただきました。好中球が刺激を受けたときにヒストンをカルバミル化すること、そしてヒルトンがカルバミル化されると著しく早く分解されるようになる一方で抗カルバミル化蛋白抗体はその分解を阻害すること、分解されず残ったカルバミル化ヒストンは単球からの破骨細胞への分化を促進することを報告しました。また、このヒストンをカルバミル化する機序は今まで知られていた機序と独立した別の機序によっており、細胞内には未知の蛋白カルバミル化機序があることが示唆されました。関節リウマチの自己抗体として中心的なものである抗シトルリン化蛋白抗体(ACPA)がカルバミル化抗原にも交差反応することが近年の研究では示されていますが、私の研究はシトルリン化抗原とは別にカルバミル化抗原が産生されることを示しており、関節リウマチの発症・病態にはシトルリン化だけではなくカルバミル化も深く関与することを示唆しています。これは、シトルリン化を軸にして考えられてきた関節リウマチの自己免疫成立機序を根本から考え直す必要性を強く示唆しています。さらにはエピジェネティック制御の一つとしてのカルバミル化の可能性も示唆しており、細胞生物学的研究の新たな一分野を切り開く可能性を秘めています。7分という短い発表時間ではこうした大きな話はなかなかできませんでしたので、残念ながら発表直後にはあまり聴衆との質疑応答は深まりませんでしたが、セッションののちこの発表の重要性に気が付いた複数の欧米の研究者とかなり深いディスカッションを交わすことができました。今後の共同研究などの仕事にもつながる可能性を秘めた、大変いい機会となりました。
一方、発表者としてではなく聴講者としても非常に大きく得るところがありました。最近の自己免疫疾患治療の新たなトピックとしてはCAR-T療法の応用が挙げられますが、これについても様々な演題がみられたとともに、CAR-T以外にも新たな細胞療法の可能性を模索する各国の研究のトレンドも伺い知れました。さらにT cell engagerの自己免疫疾患への応用などについてもエキサイティングな報告がなされており、近い将来自己免疫疾患の治療法が大きく変貌を遂げる地殻変動の地響きを聞き取ることができました。
また、留学時代のメンターや世界各国の友人、日本から来た様々な施設の友人たちとも交流することができ、そこを起点に交流が広がったことも大きな利益でした。これをきっかけにして多施設研究を新たに開始していくことができそうな手ごたえも得られました。
さて、この学会の会期中にも中東で戦争が始まるなど、世界情勢が大きく混乱しつつある昨今ですが、サイエンスの分野においては人類が一致して協力できると思いますし、それをきっかけに人の和が紡がれるのではないかと信じます。こういう時代であるからこそ積極的に海外に出ていく姿勢を維持する必要性について、改めて信念を強く持ちました。
最後になりましたが私の演題をご評価くださった選考委員の皆様、そして支援くださった財団関係者の皆様に心より感謝申し上げます。ここで得た知見そして感動と刺激をさらなる研究の原動力として、いつか必ず患者さんの治療に還元したいと思います。
慶應義塾大学リウマチ膠原病内科 米澤 江里奈
このたび、「ヨーロッパリウマチ学会発表助成者」としてご選出いただき、スペイン・バルセロナで開催された欧州リウマチ学会2025(EULAR 2025)に参加させていただきました。このような貴重な機会を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
私は、“Genetic Polymorphisms in Methotrexate Metabolism: Associations of Methotrexate Polyglutamate Concentrations and Clinical Outcomes in Rheumatoid Arthritis Patients”という演題にて、ポスター発表を行いました。
メトトレキサート(MTX)は関節リウマチ(RA)の第一選択薬ですが、薬効や副作用には大きな個人差があることが知られています。MTXは血中から早期に消失した後、細胞内でポリグルタメート化され(MTX-PGs)、その形で薬効を発揮します。近年MTX治療におけるバイオマーカーとして、赤血球中MTX-PG濃度や、MTXの薬物代謝に関わる一塩基多型(SNP)の影響が注目されています。これらの背景をふまえ、本研究では日本人RA患者を対象に、①SNPと赤血球中MTX-PG濃度の関連、②SNPとMTXの有効性および安全性の関連性を明らかにすることを目的としました。12種類のSNPに着目して解析を行った結果、いくつかのSNPが赤血球中MTX-PG濃度あるいは疾患活動性、肝機能障害と有意な関連を示しました。発表当日は、日本からの参加者のみならず海外の研究者の方々からも関心を寄せていただき、質疑応答の機会をいただくことができました。英語でのディスカッションには緊張もありましたが、大変良い経験となり、研究に対する新たな視点や刺激を得ることができました。
今回が初めての国際学会参加でしたが、自身の発表以外の時間にはさまざまなセッションを聴講し最新の知見を学ぶとともに、同じ大学から参加した先生方の発表を応援したり、興味のある分野のポスター発表を訪れて勇気を出して質問をしたりするなど、非常に充実した時間を過ごすことができました。
また、会場内の製薬企業ブースではバリエーション豊富なコーヒーサービスが提供されていたり、海外の参加者がスーツではなくカジュアルな服装で参加されていたりと、日本の学会とは異なる雰囲気も印象的で、新鮮な体験でした。
今回の学会参加を通じて、研究に対する視野を広げるとともに、国際的な発表の場で自分の研究を伝える意義とやりがいを実感しました。今後も、さらに知識と経験を深め、またこのような国際学会の場に参加できるよう研鑽を積んでまいりたいと考えております。
改めまして、このような貴重な機会をいただきました日本リウマチ財団の皆様に、心より感謝申し上げます。
昭和医科大学 医学部内科学講座 リウマチ膠原病内科学部門 柳井 亮
このたび、令和7年度日本リウマチ財団「国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表」に対する助成を受け、スペイン・バルセロナで開催された欧州リウマチ学会(EULAR 2025)に参加する機会をいただきました。本学会では、ポスターセッションにて研究成果を発表いたしました。以下に、発表の概要および学会で得た知見についてご報告いたします。
本研究は、ANCA関連血管炎(AAV)に対するリツキシマブ(RTX)寛解導入時のステロイド漸減レジメンの有効性・安全性を検討した国際共同後ろ向きコホート研究です。対象はMPA、GPA、EGPAの患者で、ステロイド初期用量と減量速度により「高用量・早期減量」「高用量・緩徐減量」「低用量開始」の3群に分類し、6か月時点の寛解率(主要評価項目)および、感染症による入院、腎不全、死亡(副次評価項目)を比較しました。結果として、6か月時点の寛解率および腎不全・死亡に関しては群間差がなく、これまでのランダム化比較試験(RCT)の結果を支持する所見が得られました。一方で、「高用量・早期減量群」では重症感染症の頻度が有意に高く、過度なステロイド減量に伴う感染リスクの増加が示唆されました。この点は、観察研究における未測定交絡因子の影響を受けたバイアスによる可能性も考えられ今後の研究デザインの改善の必要性が浮き彫りになりました。会場では各国の研究者から複数の質問をいただき、本研究の今後の課題についてより深く考察する貴重な機会となりました。
EULAR 2025では、関節リウマチ(RA)治療に関する新たなEULAR推奨(2025年版)が発表されましたが、前回からの大きな変更点は少なく、近年RA治療における画期的な新薬の登場が限定的であることが印象に残りました。一方、RA以外の疾患に関する発表が多く、筋炎やシェーグレン症候群に対するEfgartigimod、IgG4関連疾患に対するRilzabrutinib、SLEおよび難治性筋炎に対するCD19標的CAR-T療法など、革新的な治療戦略が臨床試験として報告されていました。また、抗ARS抗体症候群およびヘモクロマトーシス関節症に関する新たな分類基準の提案もありました。さらに、実臨床に近い条件で実施された複数のプラグマティック(実用志向型)臨床試験の報告も見られ、現場に即したエビデンス創出の重要性が改めて認識されました。今回、日本からの参加者および発表の少なさを実感するとともに、世界にインパクトを与えるためには、希少疾患における質の高いコホート研究の構築や、プラグマティックトライアルの推進が不可欠であると実感いたしました。
最後になりますが、貴財団からの温かいご支援は、経済的負担の軽減のみならず、精神的にも大きな支えとなり、実り多い国際学会参加の実現につながりました。改めて、心より厚く御礼申し上げます。