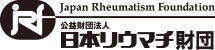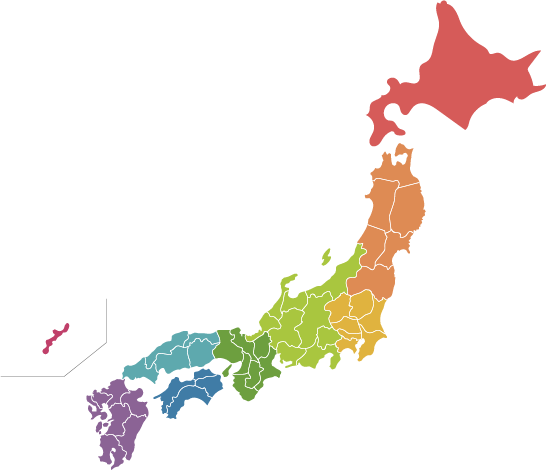医療関係者のみなさんへ
Pickup
-
財団ニュース新刊のご案内

-
令和8年度海外派遣医募集
この制度は、若い優れたリウマチ専攻医を海外に派遣・研修させ、日本のリウマチ学およびリウマチ治療対策の進歩を期待するものです。
●締め切り :令和8年3月31日(消印有効)
-
日本リウマチ財団【公式】X
リウマチ性疾患情報、講演会・研修会のお知らせ、リウマチ専門職関連情報等をタイムリーに発信しています。ぜひフォローください。