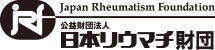日本リウマチ財団ニュース
日本リウマチ財団ニュースJapan Rheumatisim Foundation News
No.193号2025年11月号

主な内容
- 令和7年度リウマチ月間リウマチ講演会開続報
- new! オンライン診療の実践:第1回「医療側からアプローチするための有用手段」
- 第6回 EUVAS Vasculitis course 速報
- EULAR2025速報
- new! リウマチ財団「医療保険部会」からの便り
第1回「関節リウマチ診療における保険請求の留意点と社会保険制度・費用対効果評価の課題
No.192号2025年9月号
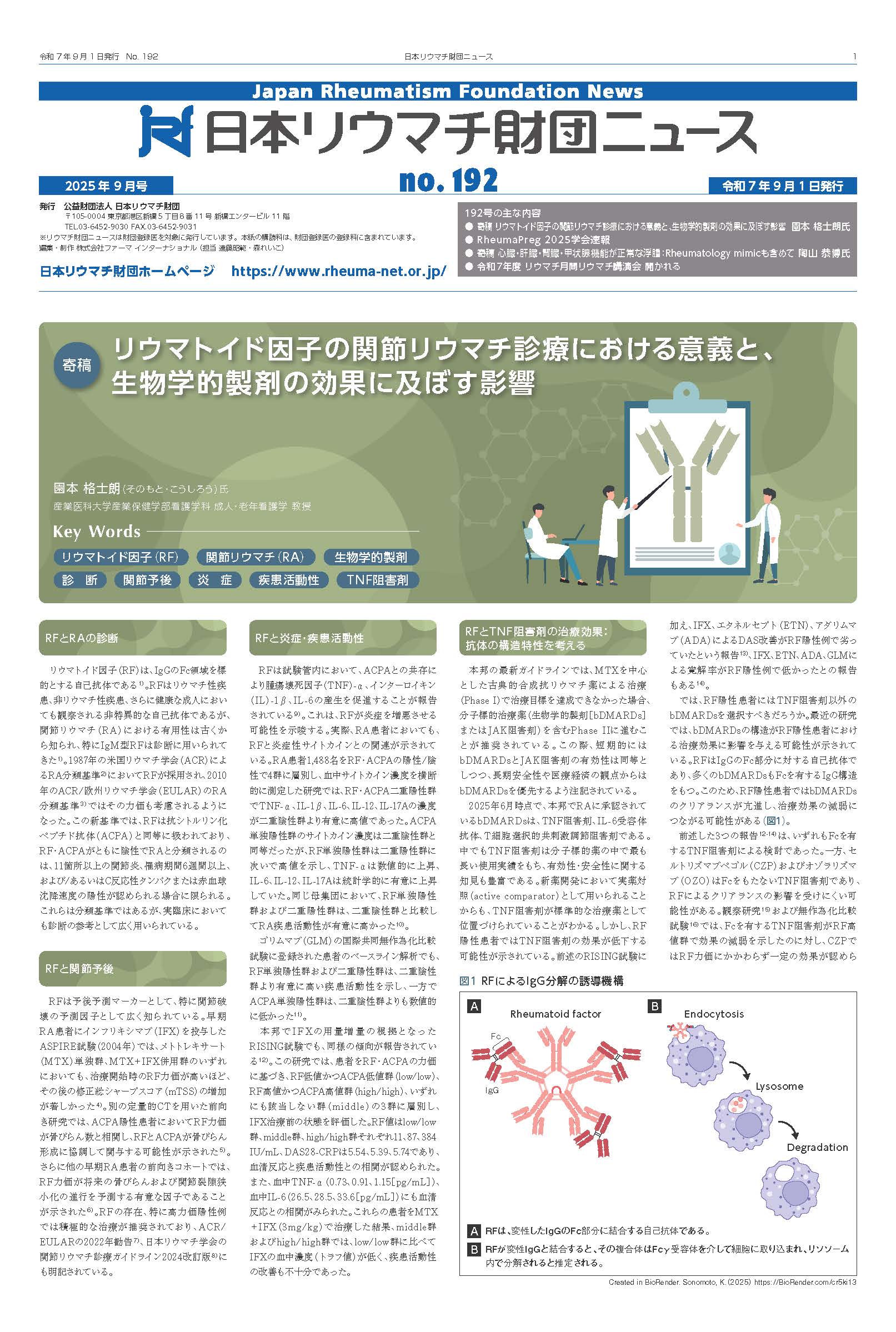
主な内容
- 寄稿:リウマトイド因子の関節リウマチ診療における意義と、生物学的製剤の効果に及ぼす影響 – 園本格士郎氏
- RheumaPreg2025 学会速報
- 寄稿:心臓・肝臓・腎臓・甲状腺機能が正常な腫瘍:Rheumatology mimic も含めて – 陶山恭博氏
- 令和7年度リウマチ月間リウマチ講演会開かれる
No.191号2025年7月号

主な内容
- 寄稿:Shared Decision Making と Advance Care Planningの臨床倫理 – 竹下啓氏
- CORA2025学会速報
- Educational Visit 2025(EV25)学会速報
- リウマチクリニックの配布資料:明陽リウマチ膠原病クリニック
- リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師のポスト:第20回十条武田リハビリテーション病院
No.190号2025年5月号

主な内容
- 令和7年度リウマチ月間リウマチ講演会 開催迫る
- リウマチ人:地域に根差し、患者さんに寄り添う – 安達 正則 氏
- 寄稿:膠原病のNPO活動 – 野村 篤史氏
- リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師のポスト“ 第19回 おあしす内科リウマチ科クリニック”
No.189号2025年3月号
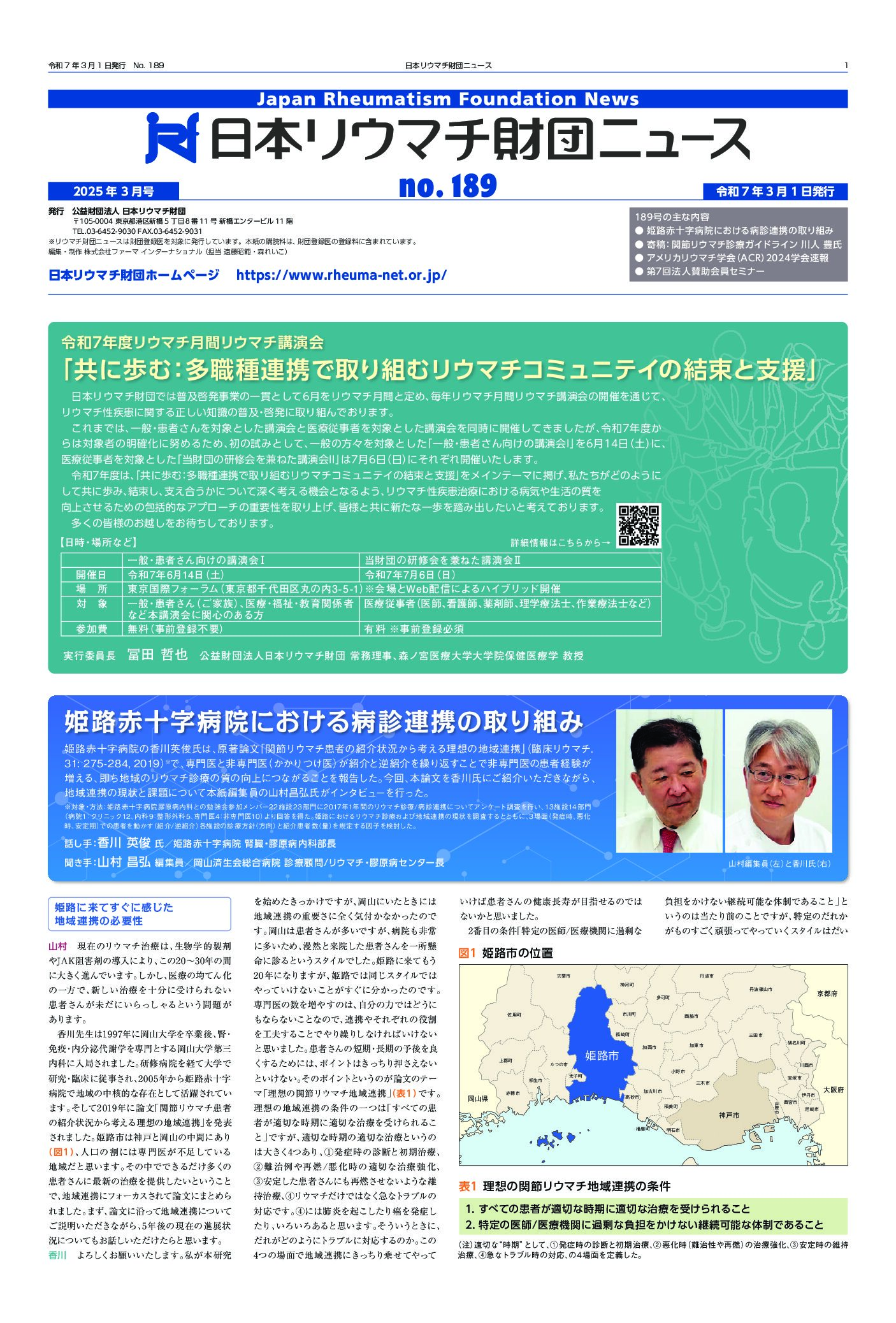
主な内容
- 姫路赤十字病院における病診連携の取り組み
- 寄稿:関節リウマチの診療指針:”日本リウマチ学会 関節リウマチ診療ガイドライン” 川人 豊氏
- アメリカリウマチ学会(ACR)2024学会速報
- 第7回法人賛助会員セミナー:添付文書の「妊婦・授乳婦の項」に関する課題と展望
No.188号2025年1月号

主な内容
- 新年のご挨拶
- 関節リウマチ(RA)に対する人工関節置換術のトピックス 寄稿:西田圭一郎先生
- GRAPPA2024 A nnual M eeting an d Trainee S ymposium学会速報
- 抗MDA5抗体と皮膚筋炎 寄稿:佐藤慎二先生
- X リウマチケア看護師、リウマチ財団薬剤師のポスト
No.187号2024年11月号

主な内容
- 寄稿:能登半島地震における災害リハビリテーション支援と有事における関節リウマチ診療について 松下 功氏
- 学会速報:第16回シェーグレン症候群国際シンポジウム
- リウマチ人:佐川 昭氏
- 学会速報:欧州リウマチ学会2024
No.186号2024年9月号

主な内容
- 令和6年度 リウマチ月間リウマチ講演会
- 寄稿 リウマチ性疾患診断のための骨関節X線所見読影のポイント:野崎 太希氏
- 特別インタビュー:織田弘美氏 第二の人生を故郷のリウマチ医療に捧げて
No.185号2024年7月号

主な内容
- 第8回国際強皮症学会 学会速報
- 第14回欧州SLE学会 学会速報
- 第21回国際血管炎学会 学会速報
- 寄稿 古くて新しい薬「メトトレキサート」:皮下注製剤の登場で何が変わったか 小山 芳伸氏
- リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師のポスト:第17回鎌ケ谷総合病院
No.184号2024年5月号

主な内容
- 令和6年度リウマチ月間リウマチ講演会 開催迫る
- 寄稿 : リウマチ性疾患におけるclinical inertia 金子 祐子 氏
- 新進気鋭の開業医:第2回 クエストリウマチ膠原病内科クリニック 林 太智 氏
- リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師のポスト 第16回 ながさき内科・リウマチ科病院