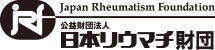日本リウマチ財団ニュース
No.191号2025年7月号
Educational Visit 25 参加報告
~Reproductive Rheumatologyをめぐる国際教育交流プログラムに参加して~
小澤廣記
聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center
責任編集:医療情報委員会委員 岡田 正人
聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center
1. 序文
2025年3月30日〜4月3日、デンマーク南部の港町スナボーにて開催された Educational Visit 25(以下、EV25)に参加する機会を得た。本プログラムは、欧州リウマチ学会(EULAR)の教育委員会が公認する国際教育イベントであり、「膠原病患者の妊娠・出産支援(Reproductive Healthcare & Family Planning)」を主題として、欧州を中心に世界各地から約30名の若手医師、研究者、患者代表が集い、分野横断的に学びを深める場となった。
EV25は、エキスパートによる講義にとどまらず、患者当事者の声を聞き、参加者同士が実践的なワークショップを通じて協働し、ひとつのコミュニティ(tribe)として連帯を育んでいくという、他に類を見ない設計がなされていた。Reproductive Rheumatology(膠原病と生殖に関わる医療)は、診療科や専門領域の枠を越えて、患者の人生設計に伴走する学際的領域である。本イベントを通じて、筆者はこの分野の本質をより多面的に理解する機会を得たと実感している。
筆者自身は、膠原病合併妊娠に関わる臨床医として、本領域のよりよい診療体制の構築と、患者との対話の質を高めるヒントを得たいという思いから本プログラムに応募し、幸運にも日本からの唯一の医療従事者として参加することができた。国や制度、文化的背景が異なる参加者と直接語り合いながら、共通する課題や異なる視点に触れられたことは、極めて刺激的で、視座を広げる経験であった。
また、特筆すべき点として、コペンハーゲンまでの渡航費を除き、コペンハーゲン〜スナボー間の移動費、宿泊費、参加費、夕食などは主催者側によって無償で提供された。これは地域企業を含むスポンサーの支援により実現されたものであり、少人数の参加者に対して丁寧に設計された、贅沢で密度の高い学びの空間であった。
本稿では、EV25を通じて得た学びと気づきを、日本の診療現場への応用という視点から報告する。

2. Reproductive Rheumatologyの歩みと挑戦 — Monika Østensen教授による開会講演より
EV25の初日には、Reproductive Rheumatologyの草創期を支えたMonika Østensen教授が開会講演を担当した。講演では、彼女の研究者としての歩みと本領域の進展が重ねて語られ、分野を切り拓いてきた情熱と実践の軌跡が浮かび上がった。
1970年代当時、膠原病と妊娠に関する医学的知見は限られており、抗リン脂質抗体症候群(APS)はまだ疾患概念として確立されていなかった。妊娠中に関節リウマチ(RA)の症状が自然に軽快するという観察結果が注目され始めていたものの、その機序は不明であり、「何らかの物質」の関与が示唆されるにとどまっていた。この仮説は後にホルモンやステロイド代謝との関連へと展開された。
一方、当時の強直性脊椎炎(AS)は「男性の疾患」として扱われており、女性患者では診断の遅れや治療選択肢の乏しさ(NSAIDsが主たる治療であった)など、構造的な困難を抱えていた。
そのような中、Østensen教授は1979年に「疾患ごとに妊娠経過に違いがあるか」「妊娠中の寛解と関連するバイオマーカーはあるか」「妊娠中の疾患活動性はどう評価されるべきか」といった先駆的なリサーチクエスチョンを提示した。当時はDAS、HAQ、BASDAIといった疾患評価指標すら整備されておらず、これらの問いに取り組むことは困難を極めたが、Østensen教授は1983年、RAおよびAS患者における妊娠中の疾患活動性に関する前向き研究を報告し、妊娠がRAの症状を改善しうる可能性を示した[1]。
さらに1980年代には若年性特発性関節炎(JIA)患者の妊娠についても研究が進められた。妊娠中には関節症状が軽快することが多い一方で、ぶどう膜炎の活動性は妊娠中も持続し、出産後に再燃する症例が少なくないことが報告された[2]。
当時はプレコンセプションケアの概念が一般的ではなく、妊娠を望む患者に対しては、医療者側の知識不足や偏見が障壁となる場面も多かった。このような状況を打開するため、Østensen教授は1991年に「母となるリウマチ患者のためのセンター(Center for Mothers with Rheumatic Disease)」を設立。患者が正しい情報にアクセスし、自己決定を支えられる医療環境の整備を推進した。
彼女の講演は、科学的エビデンスの提示にとどまらず、臨床・研究・啓発の現場における地道な取り組みと、患者への深いまなざしを通じて、現在のReproductive Rheumatologyの礎がいかに築かれてきたかを参加者に実感させるものであった。
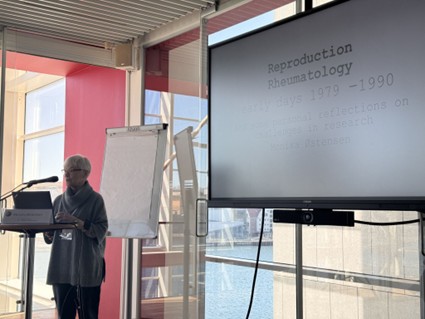
Monika Østensen 教授による開会講演。
「Reproduction Rheumatology」の黎明期(1979–1990年)を振り返りつつ、研究の困難と情熱を静かに語る姿は、いま私たちが行っている医療や研究が、先達の苦労や試行錯誤の積み重ねのうえに成り立っていることを示していた。
3.「Being a woman and a patient」──患者の視点から見たリプロダクティブ・ジャーニーのアンメットニーズ
講師:Silvia Aguilera(SAF España 副会長、ERN ReCONNET 患者代表)
本セッションでは、抗リン脂質抗体症候群(APS)の患者であり、母親でもあるSilvia Aguilera氏(SAF España副会長、ERN ReCONNET患者代表)が登壇し、膠原病患者として妊娠・出産に向き合ってきた経験をもとに、未だに多くの女性患者が直面する未充足ニーズについて実感を込めて語った。
提示された課題は、プレコンセプションケアの不在、情報や支援体制の地域差、診療科間の連携不足、ならびに妊婦が臨床研究から除外されている現状など、制度的かつ構造的な問題にまで及んだ。[3] また、医療者との信頼関係構築の難しさや、SNSやAIを通じた過剰な情報提供、さらには文化的・家庭的背景に由来するプレッシャー(例:中国における義母からの干渉)など、患者が置かれる多様な状況にも言及された。
一方でAguilera氏は、課題の提示にとどまらず、現場に根ざした具体的な解決策も複数提示した。その一部として、(1)患者が安心して意思決定に参加できる環境づくり、(2)医療者が段階的に妊娠希望を尋ねる継続的対話の重要性、(3)専門職が同席できない場合にも活用可能な共有資料・メモの整備といった提案が挙げられた。
さらにAguilera氏は、以後のワークショップにおいても建設的な発言を継続し、「患者中心のケアとは何か」という問いを多職種の医療者に投げかけ続けた。その姿勢は、単なる個人の経験にとどまらず、患者の声を臨床実践に活かすという視点を医療従事者に促すものであり、Reproductive Rheumatologyにおける患者参画の意義を改めて認識させるものであった。

写真左がAguilera氏。 Materials ScienceのPhDでもあり、情熱とバランス感覚の取れた人物。
4.「サリドマイド事件から60年、妊婦を“守る”研究へ」 – Catherine Nelson-Piercy
本セッションでは、英国King’s College LondonのCatherine Nelson-Piercy教授が登壇し、サリドマイド事件以降の妊婦に対する医薬品安全性の評価と研究倫理に関する課題を振り返りつつ、今後の方向性について包括的に論じた。
サリドマイド事件とは、1950年代末から1960年代初頭にかけて鎮静剤・睡眠薬として広く使用されたサリドマイドが、妊婦の服用により胎児に重篤な先天性障害を引き起こした薬害である。1957年に旧西ドイツで開発された本薬剤は、日本を含む多くの国で販売され、「安全性の高いつわり止め」として使用されていたが、結果として世界で約1万人、日本では約1,000人(推定)の被害が報告された[4]。この事件は医薬品の承認制度や安全性評価に大きな影響を与え、現在に至るまで薬害再発防止策の基盤となっている。
Nelson-Piercy教授は、この歴史的背景を踏まえ、妊婦を臨床研究から「除外」し続けてきたことにより生じた情報の空白(information gap)が、治療機会の喪失や意思決定の困難を招いている現状を指摘した。英国のデータでは、妊娠中に死亡した女性の約75%が医学的または精神的な基礎疾患を有していたことが報告されている[5]。しかし、多くの薬剤は妊娠中の使用に関して明確なエビデンスを欠いており、添付文書にも記載がないままとなっている。欧州において妊娠中の安全性情報が明記された薬剤は全体のわずか5%にとどまる。
特に、催奇形性リスクの評価には非常に大規模な研究が必要であるにもかかわらず、「データがないこと」が「危険であること」と同義に誤解される風潮が存在し、実際の診療判断をより困難にしている[6]。このような背景のもと、Nelson-Piercy教授は、以下の6項目を具体的な提案として提示した。
① 妊娠中の薬剤使用に関する一貫したメッセージの発信
② 妊婦の臨床試験参加機会の確保
③ 既承認薬剤に関する情報の更新
④ 保険制度の見直し
⑤ 製薬企業へのインセンティブ導入
⑥ 全国的な研究基盤の整備
これらの提案は、妊娠中の医療介入の質と安全性を高める上で重要な指針となるものである。
例えば、生物学的製剤(biologic DMARDs)の妊娠中使用に関する最新研究では、第三期まで曝露された児においても免疫系異常は認められず、ロタウイルスワクチン接種も安全に実施されたことが示されている[7]。さらに、Lancet Rheumatology誌に掲載されたレビューでは、「妊娠中において生物学的製剤による疾患コントロールの利点は、従来型DMARDsに比して明らかに上回る」との見解が示されており[8]、今後はこうしたエビデンスに基づいた診療ガイドラインの整備が期待される。
Nelson-Piercy教授は講演の最後に、「妊婦が亡くなるのは治療法が存在しないからではなく、社会が彼女たちを支援していないからである」と強く訴えた。この言葉は、妊娠中の安全性研究を単なる学術的課題ではなく、私たち医療者一人ひとりの責任として捉えるべきだという強いメッセージであり、自身の臨床実践における姿勢を見直す契機となった。
5.Reproductive Rheumatologyの未来展望 — Anne Troldborg(Aarhus University, Department of Clinical Medicine)
本セッションでは、デンマーク・オーフス大学臨床医学部のAnne Troldborg博士が登壇し、Reproductive Rheumatology分野における最新の研究動向と今後の展望が論じられた。
冒頭では、同分野における研究量の不足が浮き彫りとなった。たとえば、ACR2024における約2500件の演題のうち、リウマチ性疾患合併妊娠に関する報告はわずか21件にとどまり、その多くが後ろ向きの記述的研究であった。疾患種、抗体、治療法などが異なる妊娠例においてAPOs(adverse pregnancy outcomes)の傾向を記述するにとどまっており、前向きかつ体系的な研究の必要性が強調された。
このような背景のもと、妊娠を通じた病態解明とトランスレーショナルリサーチの推進が求められている。EULARの推奨に基づき、妊娠前、各トリメスター、産後の各タイムポイントで臨床情報(CRF)、バイオマーカー、バイオバンクを収集し、全国的・国際的な共同研究へと展開する枠組みが提案された[9]。さらに、看護師によるカウンセリング支援やRedCapを用いたデータ管理の整備も重要な要素として挙げられた。
研究成果の一例として、RA患者における自然寛解を対象とした演題#0872が紹介された。RA女性19名および健常対照14名を対象に、妊娠前および妊娠各期に採取した血液を用いてbulk RNA sequencingを実施したところ、自然寛解に関連する候補遺伝子の存在が示唆された[10]。
また、APSによる妊娠喪失の病態を解析した演題#1702では、ヒト化TLR8マウスモデル(Sle1.huTLR8tg)を用い、胎盤初期の血管形成異常、子宮NK細胞の減少、免疫細胞浸潤といった病態が再現され、TLR8の関与が想定された[11]。
抗SS-A抗体陽性妊娠の管理に関しては、妊娠16〜26週に週1〜2回の胎児心エコーを実施し、ヒドロキシクロロキンを併用するという対応が、PATCH試験などの結果に基づき国際的には推奨されつつある[12]。ただし、本邦においては現時点でこの目的でのヒドロキシクロロキン使用は適応外であり、臨床判断には慎重な対応が求められる。ただし、先天性心ブロック(CHB)の発症率は0.7〜2%と低く、予防的介入の有効性は今なお不確かである。
さらに、妊娠中のIgGの胎盤移行については、FcRn(新生児Fc受容体)を介した機序が示され、これに基づく治療応用としてFcRn阻害薬の開発が紹介された。とりわけ、重症筋無力症に対してFDAおよびEMAの承認を受けたefgartigimodおよびnipocalimabが注目されており、後者はSjögren症候群に対してもBreakthrough TherapyおよびFast Track指定を取得している[13]。抗SS-A抗体に対するFcRn阻害薬の応用は、今後の高リスク妊娠における新たな治療選択肢となる可能性がある。
本講演は、基礎研究と臨床実装の橋渡しを目指す視座から構成されており、前向き研究の推進、学際的連携、産業界との協働の必要性をあらためて確認する内容であった。
6.妊娠・授乳中の抗リウマチ薬使用:不確実性をどう伝えるか — Angela Tincani(University of Brescia, Department of Clinical and Experimental Sciences)
本セッションでは、妊娠および授乳中における抗リウマチ薬の使用に関する「不確実性(uncertainty)」の伝え方に焦点が当てられ、実臨床における情報の限界とその対応について論じられた。
はじめに、EULAR、ACR、BSRなどの国際学会から、妊娠・授乳期における抗リウマチ薬使用に関する推奨が発表されており、一見すると情報は体系化されているように見える[14]。しかし、各国の添付文書や規制の違いは依然として大きく、診療現場では不確実性を伴う意思決定が求められる場面が少なくない。
たとえばアザチオプリンは、動物実験において催奇形性が示唆されている一方で、ヒトにおける観察研究では有意なリスク上昇は報告されていない[15]。それでも、日本の添付文書では「治療上の有益性および母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること」と記載されており、使用判断において慎重さが求められる。
生物学的製剤については、胎盤移行性の違いが強調された。とくにセルトリズマブ・ペゴルはIgG構造中のFc領域を欠いており、胎盤通過性が極めて低いことから「ゴールドメダル」として紹介された。一方、エタネルセプトも比較的移行性が低いとされるが、日本の添付文書には妊娠中使用に関する明確な推奨はなく、臨床判断には慎重な対応が求められる。
授乳についても、一般に母乳中に移行した薬剤は乳児の消化管で分解されるため、生物学的利用能は極めて低いとされる。たとえばエタネルセプトについては、イタリアでは授乳中の使用が容認されている一方、日本の添付文書では「授乳の継続又は中止を検討すること」とされており、こうした国際的な運用の違いも不確実性の一因とされる[16]。
不確実性への対応策として、BresciaのRheumatology Pregnancy Clinicでの実践が紹介された。このクリニックでは、月1回の多職種合同カンファレンスを通じて、診療プロトコールの共有、難治症例のマネジメント、患者会との連携、地域小児科医との情報共有書類の作成など、多面的な支援体制が構築されている。
講演の締めくくりとして、Tincani氏は「ガイドライン、添付文書、実臨床のいずれにもギャップがあるなかで、単独の専門医による判断ではなく、多職種・多領域の連携に基づいた意思決定こそが現実的かつ望ましい」と強調した。本セッションは、情報が不十分な状況でも最善の選択を模索するうえで、診療体制や意思決定のプロセスを見直す契機となった。
7.「抗リン脂質抗体症候群における血栓・出血リスクのバランス」 — Beverley Hunt(Guy’s, St Thomas’ & Kings College/Thrombosis UK創設者)
本セッションでは、APSにおける抗凝固療法の利益と出血リスクのバランスに関し、最新の知見と臨床的課題が共有された。
APSは1988年に初めて記載されて以降、単なるSLEの付随疾患ではなく、独立した多臓器疾患としての認識が進んでいる。しかしAPSの診断は難しく、症状の多様性に加え、検査における制限(誤解を招く検査名、3種類の検査を2回に分けて測定する必要があることなど)が診断精度に影響を及ぼすとされた。APSにおける血栓形成は炎症を伴わず、静脈系・動脈系・胎盤を含むあらゆる血管床に影響し、再発部位が同一血管床に集中する傾向も特徴的である。
2023年に発表されたACR/EULARの新分類基準は研究向けに特化しており、特異度は高いが感度は低く、診療現場での使用には適さないとされた[17]。
臨床現場では、診療科によって診るAPS症例の傾向が異なる。血液内科ではDVTやPE、リウマチ内科ではSLE合併症例、神経内科・循環器内科・皮膚科・眼科などでもそれぞれ特有の病態が関与する。Hunt先生は「立場によってAPSの見える景色は異なる」と述べ、継続的な教育的連携の必要性を強調した。
検査においては、CRPやFVIIIなどの炎症マーカー上昇により、LACの偽陽性となる可能性があり、COVID-19の流行期にはこの点が見過ごされていたとの指摘があった[18]。
治療戦略としては、次のような血液学的管理が紹介された:
・isolated aPLに対しては生活指導のみ
・provoked VTE(例:妊娠中のDVT)には3〜6か月の抗凝固療法
・unprovoked VTEや二重陽性ではVKA INR 2–3
・動脈性イベントや微小血管障害にはVKA INR 3–4
・単独陽性の場合はDOACも選択肢だが慎重な判断が必要
加えて、スタチンの抗血栓効果としてNF-κB活性抑制による凝固活性の低下や血管拡張効果が紹介され、HCQは抗体価の低下と再発予防に有効である可能性があるとされた[19]。
妊娠関連APSでは、出産後の血栓リスクが51.1%と高く、肥満が重要なリスク因子であること、近年は中絶例の増加も指摘され、社会的背景を含めた対応が求められている[20]。また、CAPSではヘパリン、アルガトロバン、エクリズマブ、CYC、RTXなどの使用が報告されており、無症候性のaPL陽性者に対するアスピリン投与には慎重さが求められる。
本セッションは、APSにおける病態理解とリスク層別化、適切な治療戦略の選択、そして多診療科による協働体制の構築が不可欠であることをあらためて確認する機会となった。特に、産科的APSもAPSの一側面であり、自身の専門領域とは異なる立場から見えるAPSの姿を意識することで、診療の幅と深さを広げる重要性が強調された。
8. 産科医とリウマチ医の対話から学ぶこと
— Jacob Lykke(Department of Obstetrics and Gynecology, Hvidovre Hospital, Denmark)
— Anne Voss(Department of Rheumatology, Odense University Hospital, Denmark)
リウマチ性疾患を抱える妊婦に対し、産科医とリウマチ医はどのように連携すべきだろうか。限られた時間と情報の中で、誰が、いつ、どのように関与することで、最も安全で納得感のある妊娠管理が可能となるのか。
本セッションでは、デンマークにおけるリウマチ性疾患合併妊娠の管理体制を紹介しながら、産科医とリウマチ医がいかに協働し、患者中心のケアを実現しているかが紹介された。
デンマークにおいては、産科とリウマチ科が共同で診療を行う体制が構築されている。人口約600万人規模で全国的に整備された医療システムにおいて、妊婦に対して12週と20週での超音波検査が標準化されており、統一された周産期管理の枠組みが整っている。
RheumaPreg(リウマチ性疾患合併妊娠)クリニックでは、妊娠前から産後までの5つの時点で、産科医とリウマチ医が共同でフォローアップを実施している。妊娠前外来(Visit 1)では、情報提供とともに寛解状態や薬剤管理の評価が行われ、12週(Visit 2)と20週(Visit 3)では超音波と各診療科による定期評価がなされる。32週(Visit 4)では分娩計画に向けた管理の最終調整を行い、産後4〜5週の診察(Visit 5)では次回妊娠も見据えた情報提供とサポートが提供される。
妊娠前カウンセリングの内容も具体的に共有された。産科医は主に既往妊娠歴、妊孕性、ホルモン状況などに着目し、リウマチ医は疾患活動性や使用薬剤の影響、遺伝的背景に基づいた対応を行う。また、避妊歴や自然流産の有無、月経周期の把握がプレコンセプション戦略に重要であるとされた。
胎盤機能については、産科医が胎児由来臓器としての役割を強調し、栄養・ガス交換・蛋白輸送といった多機能性が解説された。一方、リウマチ医の観点からは、リウマチ性疾患の患者における低用量アスピリン(ASA)投与の意義が共有され、150mg/日の服用により、妊娠16週以前から導入することでpreterm preeclampsiaのリスクが0.38に低下するとのエビデンスが紹介された[21]。
さらに、胎児への薬剤曝露の影響に関しては、抗SS-A抗体の胎盤通過による胎児心疾患へのリスクが挙げられ、産科医による胎児発育不全(FGR/IUGR)への配慮とあわせて、綿密な連携の重要性が示された。
妊娠後期の診療上の課題としては、リウマチ性疾患のフレアと妊娠高血圧症候群の鑑別が挙げられた。具体的には、産科医はHELLP症候群や早産リスクを、リウマチ医はループス腎炎やCAPSの可能性を念頭においた対応が必要である。
最後に、「疾患寛解状態での妊娠」「早期からのプレコンセプション支援」「治療薬の継続的調整」「医師・患者・パートナーを含めた意思決定の共有」といった診療戦略が鍵であることが再確認された。本セッションは、多職種の視点が重なり合うことで、より安全で患者の納得を得られる妊娠管理が実現しうることを示す好例であった。
9.EV25におけるチームビルディングおよびワークショップ
EV25では、講演に加えて参加型のセッションも重視されていた。本セクションでは、チームビルディングやグループワークといった実践的な取り組みに焦点を当て、その構成と得られた学びを紹介する。約30名という少人数の構成により、参加者どうしの対話や協働が深まり、講義だけでは得られない教育効果が生まれていた。
■ チームビルディング:Day 2(4月2日)
ここでは、スペシャルゲストのManuel Knight氏のファシリテーションにより、「集団としての文化(culture)の形成」が主題となった。Knight氏は文化を“slow system”と定義し、ritual(儀式)、symbol(象徴)、heros(象徴的存在)、value(価値観)から成り立つとした。その上で、structure(構造)、strategy(戦略)、policy(方針)などの“fast system”との連携が文化形成には不可欠であると説いた。
また、high-performanceチームの構成要素として、“lean forward”の姿勢、perceived control/progress、vision/meaning、connectednessの4要素が紹介された。氏は、72%の労働者が「睡眠状態で働いている(sleepwalking)」という現実に触れ、高い成果を生むためには「自分ごと」として取り組む意識と行動変容が求められると述べた。
さらに、行動変容には“What(知識)”、“How(技術)”、“Want(意欲)”の3要素が必要であり、とりわけ“Want”の涵養が文化醸成に直結するとの指摘は示唆に富んでいた。「If you want corn – plant corn(結果が欲しければ、それに見合った行動を)」という比喩も、実践を促す強いメッセージとして印象に残った。このようなチームビルディングの機会が、参加者間の信頼関係構築と連帯感の醸成につながり、このイベントを特別なものにした。

Manuel Knight氏(左 写真中央)は、15年以上の経験を持つハイパフォーマンスチーム構築の専門家として、EV25にインスピレーションと笑いを届けた。
■ ワークショップ ①:Day 3(4月3日)
テーマ:「臨床医と患者の対話:困難な症例でのコミュニケーションの課題を探る」
本セッションでは4つのグループに分かれ、以下の臨床テーマに関して症例ベースの議論を行った
・関節リウマチと催奇形性のある薬剤
・SLEおよびAPS
・プレコンセプションカウンセリング
・男性患者に関する課題
筆者が所属したグループでは、MTXを使用中に計画外の妊娠のため受診したRA患者役とリウマチ専門医役による診察風景のロールプレイを観察した。その後、薬剤の中断・継続に関する判断や、妊娠希望を持つ患者に対する医療者の関わり方、避妊指導や不妊治療導入時の支援体制など、「患者の気持ち」と「医学的判断」が交差する場面について多角的に議論が行われた。
■ ワークショップ ②:Day 4(4月4日)
テーマ:「ワークショップ①で得られた内容を教育資材に展開する」
各グループは、前日の議論を踏まえて、患者・医療者・家族など多様なステークホルダーを対象とした教育資材の試作に取り組んだ。リーフレット、スライド、チェックリストなどの形式が検討され、筆者のグループでは、MTX使用中の妊娠リスクと妊娠可能性に関するリーフレット作成を行った。
不安を過度に煽らず、段階的に情報提供を行う工夫が重視され、ヘルスリテラシーの配慮、図表の導入、医療者向け情報の併載などの手法が議論された。患者視点とエビデンスのバランスが繰り返し確認され、内容の妥当性とわかりやすさの両立が図られた。
■ 成果報告:Day 5(4月5日)
最終日には、各グループが15分間の成果発表を行い、教育資材の草案を提示した。この活動は現在も継続中であり、完成版は2025年のEULAR(バルセロナ)におけるReHFaP Study Groupセッションで発表される予定である。
本プログラムは、単なる知識伝達にとどまらず、実際の臨床課題をもとにした多職種・多文化的な視点での議論と教材開発を通じて、今後の国際協働に向けた実践的な基盤を築く貴重な機会となった。

筆者(左から4番目)の参加したグループでの記念写真。現在もオンラインでの交流と作業が続いている。
10. 総括:EV25を通じて見えた Reproductive Rheumatology のあたらしい地平
ここまで報告してきた通り、EV25はリウマチ性疾患と生殖に関わる医療において、学際的かつ実践的な学びの場であった。南デンマーク大学の明るく開かれたキャンパスに、欧州を中心に世界各地から約30名の医療関係者が集い、5日間にわたる集中的なプログラムに参加した。
本プログラムは、リウマチ科、産科、看護、基礎研究、患者当事者といった多様な専門職の視点を交差させる構成であり、座学・対話・症例検討・教材作成に加え、文化形成を目的としたチームビルディングも組み込まれていた。
とりわけ印象深かったのは、講義で得られた知識そのものよりも、参加者間の信頼関係が徐々に育まれていくプロセスである。セッションの合間はもちろん、朝食・昼食・夕食、さらにはレクリエーションの時間を問わず、各所で自然発生的にグループができ、コーヒーを片手に活発な対話が続いていた。チームビルディングセッションを経て、イベント参加者がひとつのコミュニティTribeとして積極的に交流を深めるオープンな雰囲気が醸成されていたことは特筆に値する。患者のためという共通の目的を起点に、異なる国・文化・職種の参加者が互いの背景を語り合いながら、未来に向けた協働の糸口を探る姿は本プログラムの本質を体現していた。
また、Silvia Aguilera 氏が代弁した患者当事者の声は、従来の臨床や研究が医療者の視点に偏ってきた実態を浮き彫りにした。不安や希望といった患者の本音が十分に捉えられてこなかった現状に対し、当事者の視座を取り入れることは、今後の研究設計、教育開発、診療方針を再考するうえで欠かせない要素である。
筆者にとっては、自施設におけるケア体制や研究テーマを見直すうえで、強力なヒントと指針を与えてくれる機会となった。同時に、「小さなことから始めなさい(Start from small things.)」というMonika Østensen 教授の言葉どおり、自らの臨床現場にこそ変化の種があることを再認識した。
EV25は単なる教育イベントではなく、異なる専門性と文化背景をもった医療者が、未来の患者ケアを共に描くための共創の場であった。ここで得た学びとつながりを現場に持ち帰り、次の対話へとつなげていきたい。

Laura Andreoli (中央)とKaren Schreiber (右) がEV25の立役者。Tincani氏から参加者全員を代表してこの二人への謝辞が述べられると、会場からは盛大な拍手が送られた。

EV25を支えたFaculty member

講演やワークショップの会場となったSDU。休憩時間にも熱心なディスカッションが続いた。

レクリエーションでは、南デンマークの美しい海と町並みを参加者で堪能した。

今後につながることが確信できる最高のイベントであった。
参考文献
[1] Østensen M, Rekvig OP, Husby G. Prognosis of pregnancy in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum. 1983;26(9):1155–1159.
[2] Østensen M, Förger F. Management of pregnancy in patients with rheumatic disease. Nat Clin Pract Rheumatol. 2007;3(6):328–339.
[3] Marinello D, Zucchi D, Palla I, et al. Exploring patient’s experience and unmet needs on pregnancy and family planning in rare and complex connective tissue diseases: a narrative medicine approach. RMD Open, 2022, 8: e002643.
[4] Lee SI, Azcoaga-Lorenzo A, Agrawal U, et al. Pregnancy and chronic conditions: A nationwide analysis of linked primary and secondary care records in the UK. PLoS Med. 2022;19(6):e1004015. doi:10.1371/journal.pmed.1004015
[5] Kerstin I, Azcoaga-Lorenzo A, et al. Maternal Medication Use in Pregnancy: Population-Based Cohort Study Using Linked Primary and Secondary Care Data. BMJ Open. 2022.
[6] Riley MF. Including Pregnant and Lactating Women in Clinical Research — Moving Beyond Legal Liability. JAMA Network. Viewpoint. May 2024.
[7] Fitzpatrick E, McGirr C, Lee H, et al. Biologic DMARDs and infant immune outcomes: Rotavirus vaccination cohort analysis. Lancet Rheumatology. 2024;6(8):e553–e561.
[8] Giles I, Thorne N, Schmidt NS, et al. The time of equipoise on the use of biological DMARDs in inflammatory arthritis during pregnancy is finally over. Lancet Rheumatology. 2024;6(8):e559. doi:10.1016/S2665-9913(24)00110-5
[9] Missmer SA, et al. EULAR recommendations for a core data set for pregnancy registries in rheumatology. Ann Rheum Dis. 2021;80(1):49–56. doi:10.1136/annrheumdis-2020-218163
[10] Wright M, et al. Investigating the Natural Improvement of Rheumatoid Arthritis During Pregnancy. Arthritis Rheumatol. 2024;76(Suppl 9).
[11] Xia Y, et al. Placental Developmental Defects in a Humanized-TLR8 Mouse Model of Spontaneous Anti-Phospholipid Antibody Induced Pregnancy Loss. Arthritis Rheumatol. 2024;76(Suppl 9).
[12] Andreoli L, et al. Clinical recommendations for the management of pregnancy in women with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome: EULAR guidelines. Ann Rheum Dis. 2017;76(3):476–485. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209770
[13] Johnson & Johnson. Nipocalimab receives FDA Breakthrough and Fast Track designations. 2024. Available at: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/nipocalimab-the-first-and-only-investigational-treatment-to-be-granted-u-s-fda-breakthrough-therapy-designation-for-the-treatment-of-adults-with-moderate-to-severe-sjogrens-disease-has-now-received-fast-track-designation
[14] Forger F, et al. EULAR points to consider on the use of antirheumatic drugs in reproduction, pregnancy and lactation. Ann Rheum Dis. 2024.
[15] 佐藤真理 他. アザチオプリン使用時の妊娠・授乳管理. Modern Rheumatology. 2022.
[16] Clowse MEB, et al. Transfer of Biologics Into Breast Milk: A Systematic Review. JAMA Pediatrics. 2021;175(2):191–198.
[17] Arnaud L, Tektonidou MG, et al. 2023 ACR/EULAR classification criteria for antiphospholipid syndrome. Ann Rheum Dis. 2023.
[18] Zuo Y, Estes SK, Ali RA, et al. Lupus anticoagulant and abnormal coagulation tests in patients with COVID-19. N Engl J Med. 2020;383(3):288–290.
[19] Erkan D, Vega J, Ramón G, Lockshin MD. The effect of hydroxychloroquine on thrombosis prevention and antiphospholipid antibody levels in primary antiphospholipid syndrome. Autoimmun Rev. 2020;19(4):102491.
[20] Butwick AJ, Abreo A, Bateman BT, Lee HC, El-Sayed YY, Stephansson O. Prepregnancy maternal body mass index and venous thromboembolism: a population-based cohort study. BJOG. 2019;126(5):581–588.
[21] Rolnik DL, Wright D, Poon LC, et al. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med. 2017;377(7):613–622.