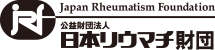リウマチに関連する病気
変形性関節症
- ①変形性関節症(OA)とは?(定義)
-
変形性関節症は、中高年の多くが罹患する疾患で、運動器症候群(ロコモティブシンドローム)の中で重要な位置を占める疾患の1つです。関節を構成する軟骨・骨・靭帯などの組織に変性・変形が起こり発症します。関節にある軟骨の変性・磨耗や、関節周囲の骨の増殖性変化(不要な部分に骨が出来てしまうこと)をきたし、二次的に関節の中にある滑膜という組織の増殖や炎症がみられることもあります。身体の全ての関節に起こり得ますが、一般的には膝・股・手・足・脊椎の関節に生じることが大部分です。手指・股・膝関節では50歳以上で発症率が増加し、80歳頃からは低下します。
 症状としては関節の痛みや腫れ(腫脹)、関節水腫(関節に水分がたまる状態)を起こし、関節の変形や可動域制限(動く範囲が狭くなること)などにより、関節の機能障害が起こります。関節の痛みと機能障害の程度によっては生活の質(QOL)に大きくかかわり、健康寿命にも影響することから、その社会的・経済的影響が非常に大きな疾患です。
症状としては関節の痛みや腫れ(腫脹)、関節水腫(関節に水分がたまる状態)を起こし、関節の変形や可動域制限(動く範囲が狭くなること)などにより、関節の機能障害が起こります。関節の痛みと機能障害の程度によっては生活の質(QOL)に大きくかかわり、健康寿命にも影響することから、その社会的・経済的影響が非常に大きな疾患です。
- ②この病気の患者さんはどのくらいいるのですか?(疫学・頻度)
-
変形性関節症は筋・骨格系疾患の中では最も頻度が高く、世界で最も患者数が急速に増加している疾患の一つです。膝・股関節の変形性関節症だけでも、現在は世界で3億人以上が罹患しており、1990年からの約30年間で10%近くの増加を示したと報告され、毎年1億5千万人もの患者が発生していると言われています。また今後も人口の高齢化により患者数が増加すると考えられています。
日本では変形性膝関節症だけでも、約800万人に疼痛などの何らかの症状があり、X線学的な関節症変化は約2500万人に存在すると言われています。発症は年齢とともに増加し、40歳以上では有病率は55%に達すると言われています。
- ③この病気はどのような人に多いのですか?(男女比・発症年齢)
-
変形性関節症は発症部位により有病率に男女間で大きな差があり、例えば女性は膝・股・手指で男性よりも罹患が多く、頚椎や肩関節では女性は男性よりも少ないと報告されています。手指・股・膝関節では50歳以上で発症率が増加し、80歳頃から低下します。
性別
変形性膝関節症は女性に多く、60歳以上では男性の約1.5~2倍の有病率になることが分かっています。変形性手指関節症では、より女性に多く、特に50~55歳の閉経後の時期に女性は男性に比較して3~4倍の発症率になります。
加齢
加齢が変形性関節症、特に変形性膝関節症の発症に関係することは多く報告されています。高齢者の関節軟骨は自然に変性・劣化していることが多く、膝関節のように可動域が大きく、負荷が大きい関節ではダメージを受けやすい状態と考えられます。変形性膝関節症の有病率は加齢に伴い増加し、70代以降のほぼ半数以上がこの疾患を患っていると言われています。
- ④この病気の原因はわかっているのですか?(病因)
-
関節軟骨の変性が病理学での特徴ですが、変形性関節症の原因は不明です。発症と疾患の進展には遺伝的要因と環境要因が複雑に関連して、相互的な作用がある多因子疾患と考えられています。
変形性関節症の発症の原因となる基礎疾患が不明なものを一次性(原発性)変形性関節症、基盤となる疾患があるものを二次性(続発性)変形性関節症と分類します。
発症の全身的要因としては加齢、肥満、性別、遺伝的要因、基礎疾患などが挙げられ、また局所的要因としては外傷、関節の不安定性、過度の力学的ストレス(労働、スポーツなど)などが挙げられます。力学的負荷がその発症に大きく関与していることから、変形性関節症は股関節、膝関節などの荷重がかかる大関節や細かい作業などの負荷がかかる手指関節に多くみられます。
- ⑤この病気の発症にかかわるものは?(誘因)
-
既往歴
既往歴とは過去の外傷や疾患を指します。具体的には外傷では、関節及び関節周囲の骨折や靭帯損傷などや、関節内の軟部組織(例えば膝半月板の損傷など)の損傷が過去にあると変形性関節症の原因となることがあります。変形性膝関節症では、前十字靭帯や半月板の損傷は特に大きな危険因子とされています。
また変形性関節症の発症に影響を与える疾患として、関節リウマチや偽痛風など様々な疾患が挙げられます。自己免疫性疾患のひとつである関節リウマチは、身体の様々な関節の炎症を起こし、変形性関節症の誘因となります。また化膿性関節炎や痛風・偽痛風など関節内に結晶が沈着するような疾患から変形性関節症が引き起こされることもあります。
肥満・生活スタイル
以前から肥満は変形性膝関節症のリスク要因とされています。肥満や筋力不足は生活スタイルと深い関係があり、変形性関節症の発症を助長する要因となります。平地を歩行する場合の膝関節にかかる負荷は、1kgの体重増加に伴い2~3kg増えるといわれており、階段昇降時には20~30倍以上になるとされています。つまり肥満であればあるほど日常的にかかる膝関節への負荷も増え、変形性関節症のリスクも増加します。
筋力不足(サルコペニア)
荷重関節では筋力不足も変形性関節症の大きな原因のひとつです。膝関節では特に大腿四頭筋という筋肉が重要な役割を担っています。大腿四頭筋や膝周囲の筋肉が衰えてしまうと膝関節が不安定になり、膝の軟骨への直接の負荷がかかるようになり、軟骨のダメージが増え、変形性膝関節症の発症へと繋がります。高齢者や女性が変形性膝関節症になりやすいのは、筋力不足に陥りやすいからとも考えられ、筋力維持のための適度な運動は推奨されます。
スポーツ歴
スポーツと変形性関節症との関連は、様々な報告があり一概には言えませんが、レクリエーションレベルのランニングでは膝・股関節の変形性関節症のリスクを下げるといわれています。またスポーツによっては、関節に捻り・ピボット動作(片脚を軸として回転や方向転換を行う動作)の多いものがあります。例えば野球での肘関節では過度の捻りが強制され、関節変形を起こすことがあります。ピボット動作の多い、卓球・バスケットボール・バドミントン・激しいダンスなどの種目では、関節や軟骨の一部に大きな負荷がかかります。そのような負荷の蓄積によって軟骨のダメージが増え、時間が経ってから変形性関節症に繋がってしまう可能性があります。
職業
膝への負荷が大きい土木業や農作業といった重労働に従事していた人は、それが変形性関節症を発症する誘因となる可能性があります。
- ⑥この病気は遺伝するのですか?(遺伝)
-
変形性関節症の30-65%は遺伝的な関与があるとされていますが、詳しいことはまだわかっていません。多因子疾患である変形性関節症の発症には種々の遺伝子が関与していると考えられています。最近ではゲノム解析の結果から膝や股関節変形性関節症での疾患感受性遺伝子が相次いで発見され、変形性関節症の発症に関わる遺伝的要因が少しずつ明らかになっています。
- ⑦この病気はどのような症状がおきますか?(症状)
-
変形性関節症は典型的には中高年者に緩徐に発症し、初期では関節の軽い痛み、違和感、こわばりを訴えることが多く、安静時には症状は示さず、関節を動かす時にだけ痛みを感じ、安静により症状が軽快します。また運動開始時だけ痛みを感じ、動き始めてしばらくすると痛みが軽快していくこともあります。病状の進行とともに運動時や荷重時の痛みが強くなり、ゴリっと鳴るような関節の異音、運動後もしばらく続く疼痛、関節液の貯留に伴う関節腫脹がみられるようになります。さらに進むと関節裂隙(関節の骨と骨の間隙間)の消失や骨棘形成(関節周囲にできる不要な骨)の影響を受けて関節が変形し、可動域制限(関節が動く範囲の制限)による関節の拘縮(動きが悪くなること)も呈するようになります。
疼痛
上記のように、病初期には関節の軽い痛み、違和感、こわばりなどが出現し、進行すると関節を動かした時に痛みを感じ、安静にすると軽快するようになります。病気の進行とともに疼痛は強くなり、夜間に痛みで目が覚めるような痛みになることもあります。
腫脹
変形性関節症は非炎症性疾患なので、関節液の貯留や骨増殖に伴う腫脹は認めますが、局所の発赤(赤くなること)や熱感はほとんど認めません。関節付近に発赤や熱感があって腫脹が著しい場合には、化膿性関節炎、関節リウマチ、結晶誘発性関節炎などの他の炎症性疾患の存在を考える必要があります。深部にある股関節を除いて、ほとんどの関節は患者さんが関節の腫れを自分で触ることが可能です。
運動制限
局所の炎症による関節包の肥厚(関節を包む袋が厚くなること)や、軟部組織の線維化による拘縮が運動制限の原因となります。病状が進行して関節の変形や関節面の不適合が認められるようになると、可動域制限がみられるようになります。
変形
関節軟骨の磨耗による関節面の変化や骨棘形成などで関節の外観が変化します。また拘縮による肢位異常も伴う場合があります。変形性膝関節症でみられる内反膝変形(O脚)が典型例で、変形性手指関節症ではへバーデン結節、ブシャール結節などの特徴的な変形を生じます。
他の身体的影響
関節の症状により精神的な影響を生じる場合もあり、抑うつ傾向になったり自殺が増加するとの報告もあります。一方で心血管疾患を生じるリスクになり得るとも報告されています。
- ⑧この病気にはどのような検査法がありますか?(検査)
-
画像検査
単純X線撮影
変形性関節症の画像診断には必須で、最初に行われるべき画像検査です。変形性関節症の単純X線像の変化では、まず関節軟骨の磨耗の程度にしたがって関節裂隙の狭小化がみられ、進行すると関節裂隙は消失します。骨性変化としては関節辺縁の骨棘形成や軟骨下骨の硬化像がみられます。時には骨嚢胞(骨の中に穴ができること)や関節内の遊離体(元々の位置から離れた、小さな骨や軟骨)もみられます。変形が高度になると関節の亜脱臼や骨の並び方(アライメント)の異常もみられます。
CT検査
変形性関節症での骨・関節の三次元的な複雑な形態の把握が容易となる検査です。診断自体には必ずしも必要はない検査ですが、手術方針の決定や術後の評価に有用です。
MRl検査
変形性関節症では関節水腫・軟骨病変・滑膜など、骨以外の軟部組織の状態の確認に有用です。
血液検査
非炎症性疾患である変形性関節症では、炎症のマーカーである血清CRP値、赤血球沈降速度値などは正常であることが多く、炎症反応が高値となる場合には関節リウマチや他の関節炎などの炎症性疾患との鑑別が必要となります。
関節液検査
変形性関節症で貯留する関節液は通常、淡黄色透明で、関節液が混濁している場合には、関節リウマチ・偽痛風・化膿性関節炎などを疑います。
- ⑨この病気にはどのような治療法がありますか?(治療)
-
治療の目的は、症状の軽減と関節機能の維持または改善です。保存療法としては、力学的負荷を減らすための減量などの生活指導、関節周囲の筋力訓練などの運動療法を行います。荷重関節では杖の使用も関節への負担が減り有効です。また変形性膝関節症では足底板、装具療法も有効です。痛みに対しては、必要に応じて薬物療法を行います。変形性関節症に使用する薬剤としては、鎮痛目的に非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)・アセトアミノフェン・トラマドールなどの弱オピオイドなどを内服または外用で使用します。また関節内にヒアルロン酸製剤や副腎皮質ステロイドを投与することもあります。保存療法を行っても効果が不十分な場合には各種の手術が行われます。
- ⑩この病気はどのような経過をたどるのですか?(予後)
-
膝や股関節の変形性関節症は末期には体重がかかると強い痛みのため歩行が困難となります。とくに膝では正座は困難で関節の動揺性が進行すると、歩く時上体が左右に揺れ脚を引きずって歩きます。股関節では股が開きにくくなったり、靴下や爪切り動作など日常動作が極めて困難となります。またバスや乗り物の乗り降り、階段の昇降が困難となります。さらに進行すると、痛みは安静にしていても常時感じるようになり、睡眠も妨げられます。
- ⑪疾患別各論<変形性膝関節症>
-
日本では約800万人が痛みや腫れなどの症状を有しており、X線写真での関節症変化は約2500万人に存在するとされています。変形性膝関節症は個人の生活だけでなく、社会全体の活動や医療・福祉政策にも多大な影響を与えている疾患です。
原疾患のない一次性がほとんどを占め、遺伝的素因などの全身性要因に加えて、膝関節への機械的ストレスにより関節軟骨や半月板、靭帯などの関節を構成する組織に変性が生じて起こります。二次性のものには膝関節の骨壊死や以前の外傷で生じた変化に加齢変化が加わって変形が生じるものがあります。
症状は初期には膝のだるさ・重さ・こわばりなどが生じ、その後病気の進行とともに疼痛や夜間痛が出ます。病気の進行とともに立ったりしゃがんだりする際や、階段の昇り降りをする際の膝痛や不安定感を感じるようになり、正座ができなることもあります。外見上はO脚を呈することが多くなります。
変形性膝関節症のリスク因子としては、肥満、女性、高齢、膝の外傷の既往、膝に負担のかかる職業などが明らかになっています。女性は男性に比べ1.5~4倍の罹患率であると報告されています。また高血圧・脂質異常・糖代謝異常や認知症などの全身性疾患との関連性も指摘されており、それらの合併数が増加するにつれて発症・進行の危険度が増すことが報告されている一方、変形性膝関節症による活動性の低下から高血圧や糖尿病を発症して、心血管疾患の合併により死亡する危険性が高いことも指摘されています。骨粗鬆症との関連は現在のところ明らかになっていません。
変形性膝関節症と遺伝子の関連性については発症や進行に関与する遺伝子・遺伝子多型が報告されているものの、現時点で病因との関連を十分に証明するのはGDF5という遺伝子のみで、本邦の理化学研究所が中心となり行なった研究結果から、GDF5が人種を超えて変形性膝関節症の発症に影響があることが確認されています。
変形性膝関節症の画像検査はX線撮影がゴールドスタンダードで、その他MRIや関節超音波検査を用います。一方で血液・尿検査などで変形性膝関節症に特異的なバイオマーカーは確立していません。
変形性膝関節症の治療は痛みなどの臨床症状の改善を目的とした、保存的治療が最重要です。変形性膝関節症に対する教育と生活習慣についての指導は短期的な除痛・機能改善に有効です。疼痛による機能低下が厳しく、保存治療では機能回復が困難な場合に外科的治療が選択されます。リハビリテーションとしての運動療法は鎮痛、身体機能改善、ADL改善に有用で、また術前、術後にかかわらず重要です。一方で物理療法については日本整形外科学会の変形性膝関節症診療ガイドラインにおいて、経皮的電気刺激や超音波治療は推奨されるものの、鍼灸治療は行わないことが推奨されています。膝装具や足底板などの装具療法は機能改善に関して推奨されています。
薬物治療では各種の鎮痛剤の内服や外用、ヒアルロン酸の関節内注射などが推奨されますが、消化管障害・心血管障害・腎障害の有無や程度などで選択を変えたり、使用期間を限定する必要があります。
サプリメント(グルコサミン・コンドロイチン、あるいはその併用やビタミンD)の鎮痛、機能改善、日常生活動作や生活の質の改善効果、および軟骨保護作用は認められていません。同様に近年話題となっている幹細胞による治療もまだ臨床的効果が認められていません。
手術治療においては、各種の骨切り術や人工関節置換術が高い有効性を示しています。
- ⑫疾患別各論<変形性股関節症>
-
変形性股関節症は股関節の可動域制限、股関節前面(鼠径部や大腿部)の運動時痛や歩行時痛がみられ、疼痛を避けるための跛行が特徴的な疾患です。X線診断による日本での有病率は1.0~4.3%で手指・膝関節に比べて頻度は低く、性別では女性に多い疾患です。発症の平均年齢は40~50歳です。
日本では原因となる疾患が明らかでない一次性変形性股関節症は少なく、先天性股関節脱臼や発育性股関節形成不全、あるいは重量物作業の職業など、発症の危険因子を有する方に発症する二次性変形性股関節症が多いことが分かっています。また変形性股関節症の発症にCALM1、GDF5という遺伝子が関与していることが明らかになっています。
変形性股関節症の治療は痛みなどの臨床症状の改善を目的とした、保存的治療がまず行われます。生活指導や運動指導などの患者教育は有用であるとされています。その上で運動療法や物理療法は短期的な症状改善に有効とされています。
薬物治療では各種の鎮痛剤の内服が推奨されますが、消化管障害・心血管障害・腎障害の有無や程度などで選択を変えたり、使用期間を限定する必要があります。サプリメント(グルコサミン・コンドロイチン、あるいはその併用やビタミンD)の鎮痛、機能改善などの治療効果に関しては一定の見解は得られていません。
手術治療においては、各種の骨切り術や人工関節置換術が高い有効性を示しています。
- ⑬疾患別各論<変形性手指関節症>
-
手指の遠位指節間関節(いわゆる第一関節)の変形性関節症であるHeberden結節(へバーデン結節)や、近位指節間関節(いわゆる第二関節)のBouchard結節(ブシャール結節)、母指手根中手関節症(CM関節症)がよく知られています。関節の安静時・運動時痛と骨性腫大(骨が突出すること)や変形が特徴的です。母指CM関節での変形が高度になると、ものをつまむ動作が困難になります。
変形性手指関節症の罹患率は報告により大きな差があり、X線学的な頻度は27-80%以上と報告されています。また米国リウマチ学会の診断基準によると、米国での罹患率は約8%と言われています。
一般的に女性が男性よりも多いことが知られており、膝や股関節は年齢とともに発症率は上がりますが、変形性手指関節症では閉経期前後の年齢での発症が多いと報告されています。遺伝性は明らかになっていませんが、Heberden結節では母娘・姉妹間などの家族内発生が、以前より知られています。また最近の報告では高脂血症が変形性手指関節症発症のリスク要因であることが分かっています。
薬物治療では症状の程度により、各種の鎮痛剤の外用や内服が行われます。この疾患では手術治療は、一般的ではありません。
【情報更新】令和5年4月