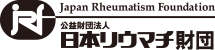関節リウマチの合併症(治療による合併症を含む)
顎骨壊死
骨粗鬆症のお薬を服用すると「顎(あご)の骨が壊死(えし)する」という話を聞いたことがありませんか?ここではこの顎骨壊死について解説します。
-
顎骨壊死とは何ですか?
-
顎骨壊死とは正確には骨吸収薬関連顎骨壊死といい、「骨吸収を抑制する薬剤に関連して生じる顎骨の壊死」のことです。英語ではAnti-resorptive agent-related Osteonecrosis of the Jawとなるので、“ARONJ”とよばれます。「骨吸収を抑制する薬剤」は骨粗鬆症に対してしばしば投与される薬剤で、具体的にはビスホスホネート製剤(商品名:フォサマック、アクトネル、ベネット、リカルボン、ボノテオ、ボンビバ、リクラストなど)、デノスマブ(商品名:プラリア)とロモソズマブ(商品名:イベニティ)の3製剤です。ロモソズマブは骨吸収促進作用と骨吸収抑制作用の2つの効果を持つ薬剤でなのですが、このうちの骨吸収抑制作用によって顎骨壊死が生じうると考えられています。
また骨吸収抑制薬以外にも、血管新生抑制作用を持つ抗VEGF(血管内皮細胞増殖因子)抗体製剤ベバシズマブ(商品名:アバスチン)によっても顎骨壊死が生じることが報告されています。そこで現在では“ARONJ”ではなく、もう少し広い範囲の用語として,薬剤関連性顎骨壊死Medication-related Osteonecrosis of the Jaw(MRONJ)と呼ばれるようになりました。
したがって同じ骨粗鬆症の薬剤でもビタミンD製剤(商品名:アルファロール、エディロールなど)、エストロゲン製剤(商品名:エビスタなど)、テリパラチド(商品名:テリボン・フォルテオ)を使用しても顎骨壊死(MRONJ)は起こりません。誤解のないように言い換えると、「ビタミンD製剤を服用中に仮に顎骨に壊死が生じても,それは薬剤関連性顎骨壊死とはよばない」ということです。

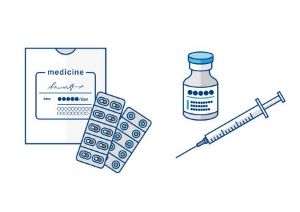
-
ビスホスホネート製剤を服用していると必ず顎骨壊死が起こるのでしょうか?
-
ビスホスホネート製剤を服用しても必ず顎骨壊死を発症する訳ではありません。いくつかの報告があるのですが、経口のビスホスホネート製剤であれば10万人年あたり1件程度といわれています。わかりやすく言うと、「10万人の人が1年間経口ビスホスホネートを服用すると。約1名に顎骨壊死が生じる」ということです。この数字をご覧になってどう感じますか?頻度は決して高くはない、むしろかなり低いという印象ではないでしょうか。ただビスホスホネートは骨に年の単位で沈着するので、服用が長期に及べば顎骨壊死のリスクは徐々に上昇します。4年以上の服用で顎骨壊死のリスクが上昇し始めるという報告もあります。
またこれらの骨吸収抑制剤を悪性腫瘍の骨転移(転移性骨腫瘍)に対して使用した場合には、顎骨壊死の発生率は100倍程度上昇するといわれています。骨粗鬆症治療における顎骨壊死とは区別して考える必要があるでしょう。1年間で

-
関節リウマチでは顎骨壊死が起こりやすいのでしょうか?
-
 関節リウマチには骨粗鬆症がしばしば併発するので、リウマチ患者さんのなかにはビスホスホネート製剤を服用したり、デノスマブの皮下注射を受けていたりする方も多くいらっしゃると思います。
関節リウマチには骨粗鬆症がしばしば併発するので、リウマチ患者さんのなかにはビスホスホネート製剤を服用したり、デノスマブの皮下注射を受けていたりする方も多くいらっしゃると思います。顎骨壊死の発症・増悪因子にはグルココルチコイド(副腎皮質ステロイド)製剤の使用と口腔内衛生環境の悪化があります。関節リウマチでは唾液分泌が低下することがあり、また手指の変形が進行すれば歯磨きの際に磨き残しが生じます。その意味でリウマチ患者さんでは通常の骨粗鬆症患者さんに比べて、顎骨壊死の発症頻度が高いことが予想されます。ただ残念ながら、具体的にどのくらい顎骨壊死の頻度が高まるのかについて定まった数字は出ていません。
また、癌・高齢・透析も顎骨壊死のリスク因子です。いずれにしても定期的に歯科健診を受けることが、とりわけリウマチ患者さんにとっては大切になるでしょう。
-
なぜ顎骨だけに壊死が起こるのでしょうか?
-
 もっともな疑問ですね。ビスホスホネートやデノスマブは全身の骨に分布するのに、なぜ顎骨だけに壊死が起こるのかという質問です。すべての理由が明らかにされている訳ではありませんが、理由のひとつは顎骨がさらされている環境、つまり口腔内細菌の存在です。特に抜歯などの外科的処置を受けた場合、顎骨はこの口腔と直接交通することになります。したがって口腔内衛生環境の悪さが顎骨壊死の発症因子・増悪因子となるのです。
もっともな疑問ですね。ビスホスホネートやデノスマブは全身の骨に分布するのに、なぜ顎骨だけに壊死が起こるのかという質問です。すべての理由が明らかにされている訳ではありませんが、理由のひとつは顎骨がさらされている環境、つまり口腔内細菌の存在です。特に抜歯などの外科的処置を受けた場合、顎骨はこの口腔と直接交通することになります。したがって口腔内衛生環境の悪さが顎骨壊死の発症因子・増悪因子となるのです。また顎骨にかかる咬合力も要因のひとつであると考えられています。成人男子では平均で60kgもの力が毎日繰り返し顎骨にかかるのですから、壊死が顎骨に起きてもさもありなんという訳です。
さらに顎骨は全身の骨のなかで新陳代謝がもっとも速い組織であるために、服用したビスホスホネートが顎骨に高濃度に沈着しやすいことも理由のひとつ考えられています。
-
何がきっかけで顎骨壊死が起こるのでしょうか?
-
多くは抜歯などの外科的処置とそれに伴う感染を契機に発症します。もちろん外科的処置がなくても顎骨壊死が生じることもあります。
-
顎骨壊死の症状と治療
-
顎骨壊死の症状は歯肉の疼痛や腫脹,歯の脱落です。抜歯部の顎骨が肉芽組織で覆われずに口腔内に露出したまま(ドライソケット)になります。また壊死に陥った骨が腐骨となれば膿がたまります。膿は腐骨部から口腔内や皮膚へ形成された瘻孔を通して排膿されます。
顎骨壊死の確定診断と治療は口腔外科専門の歯科施設で行う必要があります。最近ではテリパラチド(PTH製剤)の有効性が報告されてはいるものの,形成された腐骨は外科的に切除することが必要です。
-
顎骨壊死を予防するためには抜歯の際にビスホスホネートをやめなくてはいけませんか?
-
2016年に出された骨吸収薬関連顎骨壊死に関するポジションペーパー1)では、原則的に歯科治療の前にビスホスホネートを休薬する必要はないとしています。その理由として、半減期2)が2年~3年のビスホスホネートを歯科治療前に3カ月休薬しても顎骨壊死の発症予防に効果があるかは疑問だからです。つまり、休薬を積極的に支持する根拠には欠けており、さらに言えば、ビスホスホネートを休薬することで生じる骨折リスクの上昇が顎骨壊死予防というベネフィットを上回る可能性もあります。
ただし、ビスホスホネートの投与期間が長期に及んでいたり、グルココルチコイド投与などのリスク因子があったりする場合で、かつ歯科処置に時間的猶予がある場合には、治療前に2か月間の休薬をすることもあります。この場合、創傷治癒が完成した時点で、歯科医師の指示のもとにビスホスホネートを再開します。
1)ポジションペーパーとはガイドライン(指針)とはいえないものの、その疾患に携わるものが共有すべき考え方のことです。
2)この場合の「半減期が2年~3年」とは「ひとたび骨に沈着したビスホスホネートが半分に減少するまで2年~3年かかる」という意味です。
-
顎骨壊死を予防するためには?
-
顎骨壊死にとってもっとも大切なことは予防です。顎骨壊死は感染が引き金となって発症・増悪します。したがって口腔衛生の改善と感染対策を徹底することが重要です。気軽に相談できるかかりつけの歯科医師を持ち、定期的な歯科クリーニングを欠かさないようにしましょう。

【情報掲載】令和6年8月